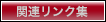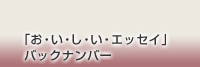沖縄県は、まことにもってイモ料理の発達したところである。なかでもサツマイモ料理は極めて多彩であり、おそらく我が国一のイモ料理文化を色濃く持っているといっても間違いはないであろう。なにせ今はサツマイモと呼んでいるイモも、元をたどれば琉球から薩摩に伝えられた根茎植物なのである。
沖縄ではイモのことを「ンム」と言う。煮たイモは、ニーンム。沖縄独特の水イモである田芋は、ターンムである。代表的なイモはサツマイモで、皮が厚く、中は紫色で味はポクポクしていて実にうまい。ターンムも薄紫色をしていて、味も香りも素晴らしい。イモは繁栄につながるめでたい食べ物とされているから、特にハレの日の料理には欠かせないのである。

最も一般的な料理は「ンムニー(ンム煮)」 である。「ドゥルワカシー」という料理は大変有名で、茹でたターンムの皮をむき、すり鉢でつぶす。次にムジ(ズイキ)をゆがいてから切ってターンムに加え、シイタケ、かまぼこ、豚肉のあられ切りを豚脂で炒めてから塩と醤油で味付けした具を混ぜる。これをとろ火で煮たものである。
「ンムクジプットゥルー」は、水に溶いたサツマイモのでんぷんに味噌とおろし生姜、ニラを加えてから菜種油をひいた鍋で焦がすぐらいに焼いたもの。「ンムクジアンダギー」は、炊いてつぶしたサツマイモとサツマイモでんぷんを半々に混ぜ合わせてから手のひらで丸めて平らにし、油で揚げたものだ。「ターンムデンガク」はターンムを炊いて皮をむき、四角に切る。湯と一緒に鍋に入れ、白砂糖でトロリとするまで弱火で炊いたものである。
これらの料理は、イモを茶請けとして食べるものがほとんどだから、一種の料理菓子のようなもので面白い。

中国の珍しいデザートに「三不粘」がある。現在の中国でも、北京の歴史ある料理屋だけしか作れない幻のデザートだという。卵黄に白砂糖を加え、緑豆の粉末を加え、油を張った鉄鍋の高熱の中で急速に何百回も叩くようにしてかき混ぜて作る。
こうしてできた三不粘は強い表面張力を持っていて、皿の上に載せても皿に粘かずにゆらゆら揺れている。箸で取ろうとしても箸にも粘かないので、小ぶりのチリレンゲですくい取る。口に入れて噛んでも、歯にまったく粘かない。すなわち、皿に粘かず、箸に粘かず、歯にも粘かないので、三不粘の名がついたという。
食べると何とも言えぬ芳香と快い甘みが口中に広がり、全体としてはゼリーではなく、求肥のようなものでもなく、強いて言えば、搗きたての柔らかい餅の歯ざわりだそうだ。口の中に入れた三不粘をそのまま噛み続けていると、いつの間にか、すっとのどを通っていってしまうという。
この三不粘、名の知れた料理人でもすぐ真似ることができるような代物ではない。とかく中国には昔からこのように特殊技術を身につけている人が少なくない。米一粒の上に何百字という漢字を書いたり、仏像画を描いたり、さまざまな野菜を使って実に芸術的な食卓の飾り物を作ったり。とにかく、三不粘のことを知っただけでも、中国の食の深さがよくわかるというものである。
一方、この三不粘のように女性的とでもいってよいような名菓とは逆に、とても男性的な菓子もあるのが、この国である。たとえば「焙羅梨」というものは、切った餅を蒸し上げ、それに小麦粉を混ぜて求肥のようにし、それを皮にして中に肉餡を包んでから天ぷらにして食べる大胆なものである。
中国には、菓子に味噌や醤油、酢、?(納豆)、?酥(チーズ)、酸?(ヨーグルト)などの発酵食品を加えたものも少なくない。日本のお菓子屋さんも一度現地をまわって見てきて、参考にされるのもよいのではないだろうか。
小泉武夫(こいずみ たけお)
東京農業大学名誉教授(農学博士)。 文筆家。NPO 法人発酵文化推進機 構理事長。昭和18 年、福島県の醸 造家に生まれる。専攻は醸造学、発 酵学、食文化論。世界中の民族の食 文化を調査し、多くの著作や講演、 テレビ出演などを通して、そのすばらしさ・楽しさを広く伝えている。 主著・近著に『酒の話』(講談社現 代新書)、『発酵』(中央公論社・中 公新書)、『くさい食べもの大全』(東 京堂出版)、『食のベストエッセイ集』 (IDP 出版)、『猟師の肉は腐らない』 (新潮社)など。1994 年から日本経 済新聞夕刊に掲載している「食あれば楽あり」でもおなじみ。