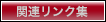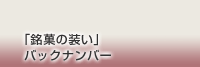![]()
美味、津軽気質

青森県弘前市といえば、まもなく「ねぷたまつり」の季節である。この祭り、弘前では「ねぷた」、青森市では「ねぶた」と濁る。地元は、この呼び方を混同されるのを嫌う。一事が万事、伝統を容易には変えないのが津軽気質である。
たとえば、弘前には、恐ろしく手のかかるために「馬鹿塗」と呼ばれる津軽塗がある。楽な技法を導入せず、馬鹿がつくほど丁寧な作業を重ねて生まれる、丈夫すぎるほど丈夫な漆器である。しかし、それが津軽独得の風土をなし、異能の人物を数多く生み出しもしたし、旅人を惹きつけてもいる。
今回、開雲堂の「卍最中」をいただき、お菓子の津軽気質に出合った気がした。明治生まれのこの最中、優しい味を頑固に守ってきたものに違いないのである。
開雲堂の初代木村甚之助は、津軽の地主であったが、農地の多くを津軽藩主に献上し、菓子屋に転身したという珍しい出自の人物である。明治12年(1879)、弘前で木村菓子店を創業、2代目を東京の名店・塩瀬に修業に出し、2代目甚之助のときから開雲堂と改称した。
「卍最中」は明治39年(1906)、初代の創製。藩への貢献によって、津軽藩の旗印である「卍」の使用を許されたという。「有明」最中、桜の季節限定の「つともち」など、2代目も多くの銘菓を残した。
3代目が木村直助。直助が亡くなって、現在は夫人の木村ノブが4代目を継いでいる。直助は民芸協会に入会し、民芸関係の人々と交流して、津軽焼の収集なども行った。弘前の銘菓「干乃梅」を津軽焼の壺に入れて売り出したのは、この人ならではの工夫である。
さて、「卍最中」の24個入りの箱の包装を解いて、掛け紙を見、「アッ」と思わず声をあげてしまった。なんと美しい、芹沢介の絵。緑とピンクと黄で、さっと描かれた風景は岩木山だろうか。
開雲堂では他にも棟方志功、武者小路實篤らの絵による豪華な掛け紙を用いている。逸品は3代目の親しかった棟方のみみずくの絵で、これは春の和菓子専用だ。
「卍最中」に戻れば、掛け紙を取ると箱は、格子模様の布を貼り込んだようなデザインであった。中身は、6センチ角の最中が二段にぎっしり。皮はさくさく、小豆の粒を散らした手亡豆の白餡はとろりとやわらかい。うっかりすると、何個でも食べてしまう。
弘前に「卍最中」あり、と言うほかはないおいしさだ。
文/大森 周
写真/太田耕治
開雲堂
弘前市大字土手町83
TEL.0172(32)2354