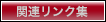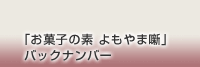![]()
日本のお菓子の歴史が、ここから始まりました。

三温糖
狂言『附子』には砂糖が登場します。大事にしている砂糖を留守中に召使が食べないかと気がかりな旦那が「これは附子といって猛毒で、匂いを嗅いだだけでも死んでしまうぞ」とおどかして出掛けます。太郎冠者が壷をあけてみると、じつは砂糖。喜んで全部なめてしまい、主人の大事にしている茶碗を割って泣いています。主人が帰ってくると、「貴方様が大事にしていらっしゃる茶碗を割ってしまったので、死んでおわびしようと思って、猛毒の附子を全部なめましたが、死ねません」。

上白糖
当時(たぶん室町時代)、砂糖は大のおとなが隠匿(?)したり、「うもうて死ぬる(あまりにおいしくて死にそうだ)」と大喜びでなめたりする貴重品だったことがわかります。
砂糖は奈良時代の後期、中国から鑑真が伝えたといわれています。正倉院御物の記録には「蔗糖二斤十二兩三分」(2キロ弱)とくわしい記録があります。当時はもっぱら皇族や貴族の医薬として、痰を切ったり唇の荒れを治したりするために使われていました。この事情は平安時代も変わらず、『源氏物語』や『枕草子』にはまだ砂糖は登場しません。
初めは黒い蜜のようなものだったらしく、狂言でも太郎冠者が「黒うどんみり(黒くてとろり)として、うまそうな物じゃ」と形容し、水飴をなめるようなしぐさをします。実際、鎌倉時代の本には「飴糖」や「蜜糖」などの字が現れます。
砂糖がその名のとおりさらさらとした「砂のような糖」となって一般化したのは江戸時代でした。江戸時代の人々はいっぺんに砂糖が好きになったらしく、世の中が平穏になるにつれて砂糖の輸入量は飛躍的に増加していきました。当時の百科事典には「白沙糖」、「氷沙糖」、「黒沙糖」などが台湾、ベトナム、福建、寧波(ニンポー)、タイ、沖縄などから入って来るとあります。

和三盆
幕府はあまりの輸入量に国内で作ることを考え、享保12年(1727)にサトウキビの苗を吹上御苑と浜御苑に植えさせ、黒砂糖54㎏余りが採れたのが、国内での製糖の始まりといわれています。こうして砂糖は日本のお菓子と料理になくてはならないものとなっていきます。
砂糖は黒糖(黒砂糖)、赤糖、白下糖、車糖(白砂糖、上白糖)、ざらめ糖、グラニュー糖、粉糖(パウダーシュガー。白ざらめ糖を細かく粉砕したもの、洋菓子によく使われる)、角砂糖など種類が多彩で、用途に応じて使い分けられています。
しかし、日本の砂糖の特徴は、なんといっても砂糖を日本の食文化、ことに高級和菓子に適するように改良を試み、苦心の結果、独自の砂糖を完成させた点にあります。ことに、糖液を煮つめてアクを抜き、練り上げ(研ぐ、あるいは揉む、といいます)、数日かけて作る「和三盆」は、独特の風味となめらかさで高級和菓子の基礎をなすものとして賞用されています。
美しく、おいしくて上品な和菓子には、地味な砂糖づくりの段階から日本人の舌と心と努力が込められています。
大塚 滋 Otsuka Shigeru
食文化研究者。新潟県生まれ。大阪大学理学部化学科卒業、理学博士。大阪府立大学教員、ウスター実験生物学研究所(米・マサチューセッツ州)研究員、武庫川女子大学教授、同大学大学院教授等を経て退職。著書に『味の文化史』(朝日新聞社)、『食の文化史』(中央公論新社)、『パンと麺と日本人』(集英社)、『世界の食文化』(共編/農山漁村文化協会)ほか多数。