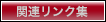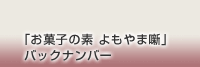![]()
柿は、日本の秋の風景を思い起こさせるなつかしい「朱」色の甘みです。
学名は「ディオスピロス・カキ」。
神が食べる果物のようにおいしい、という意味です。

柿は中国北部、朝鮮、日本で古くから栽培されており、日本へは奈良時代(8世紀)に中国から渡来したという説が有力のようです。
一方、「歌聖」と称される飛鳥時代の歌人、柿本人麻呂の姓について「敏達天皇(おそらく6世紀中頃)の御代、家の門のそばに柿の木があったのが名の由来」と書いた平安時代の書物があり、両説には200年ぐらいのへだたりがあります。いずれにしても、ずいぶん古くから日本で栽培されていたことは確かです。
明治の頃、日本に来た欧米人には柿の木が珍しかったらしく、明治18年に日本の来たフランスの小説家ピエール・ロティは「ミカンより美しい色をした、ちょうど褐色の黄金の球のようにすべすべしてピカピカ光る柿が、いたるところに枝いっぱいに実っているのに出会った」と感動しています。
この年にはロンドンで園芸博覧会が開かれ、初めて日本から鉢植えの柿が出品されましたが、イギリスの雑誌には「すがすがしい匂いがする。熟したものはその味がすばらしい」と手放しでほめられています。
植物学者も日本独自の果物と思ったらしく、学名は「ディオスピロス・カキ」と命名し、しかも属名のディオスピロスは「神が食べる果物のようにおいしい」という意味。イタリアやスペインでは、「カキ」と日本語そのまま呼んでいます。
 柿には多くの種類がありますが、大きな特徴は甘柿と渋柿があることで、実が幼いうちはみんな渋く、熟すにつれて渋が抜けるのが甘柿、抜けないのが渋柿です。
柿には多くの種類がありますが、大きな特徴は甘柿と渋柿があることで、実が幼いうちはみんな渋く、熟すにつれて渋が抜けるのが甘柿、抜けないのが渋柿です。
柿渋の本体は日本人によって発見され命名された「シブオール」というタンニンの一種で、甘柿の場合、熟すにしたがって水に溶けなくなるので、舌に感じなくなります。だから渋が「抜ける」というより「舌に感じられなくなる」といった方が正しいかもしれません。同じ現象は渋柿を干したり、アルコールや二酸化炭素、温湯などで処理する(醂す)ことによっても起こるので、干し柿やさわし柿は甘くなるわけです。
干し柿は串柿、吊るし柿、巻柿があり、新年の重要な供え物となっています。柿はたくさん実がなるので「多産」への祈りだったといわれます。ここ数十年、日本は少子化が進んでいますので、今また串柿の出番がまわってきたといえるかもしれません。また、熟柿をスプーンでアイスクリームのようにすくって食べるのも楽しいものです。
柿は果物のなかでは珍しく酸味がなく、独特の風味のせいもあって缶詰やジュースなどにはされませんが、甘さが上品で強いので、和菓子の材料として使われてきました。柿羊羹は普通、干し柿の果肉をつぶして砂糖、寒天などを加えて作られ、独特の風味が喜ばれます。岐阜や広島の柿羊羹が知られています。
 柿の美しい色はカロテノイド系の色素で、これが私たちの体内でビタミンAに変わります。またビタミンCなども多く含み、栄養的にすぐれた果物です。さらに柿のヘタや葉には薬効成分があるといわれています。「柿が赤くなると医者が青くなる」という言葉があるということです。
柿の美しい色はカロテノイド系の色素で、これが私たちの体内でビタミンAに変わります。またビタミンCなども多く含み、栄養的にすぐれた果物です。さらに柿のヘタや葉には薬効成分があるといわれています。「柿が赤くなると医者が青くなる」という言葉があるということです。
大塚 滋 Otsuka Shigeru
食文化研究者。新潟県生まれ。大阪大学理学部化学科卒業、理学博士。大阪府立大学教員、ウスター実験生物学研究所(米・マサチューセッツ州)研究員、武庫川女子大学教授、同大学大学院教授等を経て退職。著書に『味の文化史』(朝日新聞社)、『食の文化史』(中央公論新社)、『パンと麺と日本人』(集英社)、『世界の食文化』(共編/農山漁村文化協会)ほか多数。