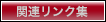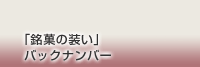![]()
名物蘇って、銘菓を生む

「木守」とは、柿の実を収穫する際に、来年の豊作を祈って、木に一つだけ採らずに残しておく実をいう。俳句では「木守」のほかに「木守柿」ともいい、冬の季語として用いている。
だが、高松市の老舗三友堂の銘菓「木守」の菓銘は、そこから直接とったものではない。「木守」という銘をもつ茶の湯の茶碗にちなんだものだ。その茶碗をめぐっては、次のような逸話がある。
あるとき、千利休がいくつかの楽茶碗をお弟子さんたちに選び取らせたとき、一つだけ残った茶碗があった。利休はそれを、木守柿のように一つだけ残ったという意味で、「木守」と名づけたという。この利休ゆかりの赤楽茶碗は、後に高松藩主松平家に献上され、名物として名高かったが、惜しくも関東大震災で壊れてしまった。
三友堂は明治五年創業。初代はもと高松藩につかえた人で、高松松平家とのえにしは深い。震災で失われた「木守」が、これを惜しむ人々の手で、残った断片を入れて再現されたとき、二代目が松平家の名物蘇生を祝って、銘菓「木守」を創案した。昭和の初めのことである。現在の当主、大内泰雄さんは四代目。
「木守」は、干し柿入りの小豆餡を、糯米の薄い手焼きのせんべいで上下からはさんだお菓子。
十二個入りの箱は、緑色の松竹梅の絵をあしらった気持ちのよい包装紙がかけられている。掛け紙は淡く描かれた枝柿ひとつで、箱はモスグリーンの和紙張り。中のお菓子は、一つ一つしっかりした紙に包まれている。包み紙には高松松平家の葵の紋と、茶碗「木守」の高台内の渦巻きを模したという模様が入っている。全体におおらかな、武家風ともいえる風格を感じさせる包装である。
味は、柿の実の甘さを巧みに生かしているところが、自然の甘味というものを、改めて思い起こさせる。手焼きでしか焼けないという皮も、口のなかでスッと溶ける。
文/大森 周
写真/太田耕治
三友堂
高松市片原町1-22
TEL 087(851)2258
FAX 087(822)2936