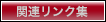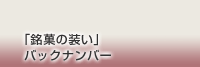![]()
海香る酒田みやげ

竹久夢二の、酒田からの知人宛の手紙に、「吹雪で北国らしい夜を過ごしています」という言葉がある。日付は1月30日だから、まさに酷寒の季節だ。
酒田の羊羮「呉竹」は全国に知られる銘菓だが、「呉竹」に使う青海苔は、そういう厳冬期に、庄内浜の吹浦で採取されるものだという。芭蕉が「奥の細道」の旅で、「あつみ山や吹浦かけて夕すゞみ」と詠んだ場所だ。「あつみ山」は鳥海山。その鳥海山から流れ出る伏流水のために、吹浦では良質の青海苔がとれる。
寒中にとった青海苔を乾燥させて保存し、使うときに石臼で挽いて香りを生かす。餡はいんげん豆の一種で、白い小粒の手亡を用いている。
「呉竹」の店・小松屋は天保3年(1832)創業という老舗で、初代小松又三郎から数えて、現当主の小松尚さんは9代目にあたる。営々と「呉竹」の味を守り続ける一方、庄内地方で最も早く洋菓子を手がけたのも、この店だ。
「呉竹」の名は明治41年、ときの宮内省侍従長・東久世通禧がこの羊羮を詠んだ和歌「沖津藻をとりあわせたるくれ竹の緑の色は千代とかわらじ」にちなむ。呉竹は真竹のことだが、和歌では、「千代」にかかる枕詞である。
さて、その「呉竹」が届いた。長方形の箱を包むのは、小松屋のロゴと「酒田八景」の版画をあしらった、青海苔の色を表したというダーク・グリーンの包装紙。包装を解くと、掛け紙は「酒田八景」中の、芭蕉の「あつみ山や」の句も入った「日和山眺望」の図。箱の蓋を開くと、中身は「呉竹」羊羮と「煉羊羮」、「呉竹最中」の詰め合わせであった。羊羮はどちらも本物の竹の皮で包み、最中の個包装も、透明な紙に呉竹の緑を刷り込んで美しい。
真っ先に手が出たのは「呉竹最中」。青海苔の入った柔らかい餡がとろりと口のなかで溶ける。輪切りにした竹の節の形もおもしろい。小豆の渋をいかして黒く黒く炊き上げるという「煉羊羮」も小松屋自慢の商品で、これぞ羊羮という口あたりだ。
正岡子規は「呉竹」羊羮を、「青幽なる色調、気品ある風味類なし」と評したというが、色、味、まさにその通り。小松屋に感服していただいた。
文/大森 周
写真/太田耕治
小松屋
山形県酒田市日吉町1の2の1
TEL 0234(22)5151