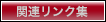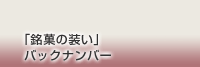![]()
宿場名物の風味を偲ぶ

旧東海道の岡崎宿跡は、現在の国道1号より1本北寄りの道にあたる。島町交差点を北に入り、道なりに東へ曲るあたりが、旧岡崎宿の中心部、伝馬通り。戦災にあった岡崎では、旧街道の家並みも戦後のものだが、それでもどこかに、宿場の面影をほのかに残している。
岡崎名物の銘菓「きさらぎ」「あわ雪」で有名な、備前屋もこの一角にある。天明2年(1782)創業といえば、今日まで続いている東海道の名店としては、屈指の老舗といえるだろう。現在の社長、中野敏雄さんが8代目。備前屋の屋号は、江戸初頭に岡崎で善政を行った伊奈備前守忠次という家康の忠臣にちなむものではないかと、中野さんが随筆で書いておられる。
銘菓「あわ雪」は、3代目が明治初期に創製したものだが、古書にも「三州岡崎東の駅口に茶店あり 戸々招牌をあげて豆腐を賣る其製潔清風味淡薄にして趣あり 東海道往来の貴族賢輩と雖も必輿を止て賞味し給ふ 東海道旅糧の一好味と謂ふべし」と記されている、江戸時代に岡崎宿の茶屋で供していた「あわ雪豆腐」がなくなるのを惜しんだ3代目が、菓子にその名を残したものだという。
「あわ雪」の4種類(スタンダードな茶山、純白、桃花の3種と鹿の子)詰め合わせは、清流の浅瀬の底の小石を描いたような模様の包装紙で包まれている。
包装を解くと、堂々たる桃色の菓子箱に、掛け紙は広重の東海道五十三次の「岡崎」をモノクロで刷り、朝顔のちぎり絵をあしらって格調高い。箱の中には、さらに1種類ずつ、それぞれ色を変えた色紙の短冊を斜めに貼ったような模様の箱におさめた「あわ雪」の棹が4本、きっちりと詰まっている。
「あわ雪」の製法は、新鮮な卵白に、寒天と砂糖で作る錦玉液を溶かし込んで、泡だてるというもの。「茶山」は抹茶、「純白」は白双糖、「桃花」は桃の果汁、「鹿の子」は蜜づけの北海道小豆粒で、それぞれ味つけをしている。いずれも実にきめ細かで、上品な味だ。
「あわ雪」の食べ方は人それぞれだと思うが、冷やして食べると、一段とおいしく、それぞれの味も際立つようだ。
文/大森 周
写真/太田耕治
備前屋
愛知県岡崎市伝馬通り2--17
TEL 0564(22)0234
FAX 0564(25)1829