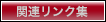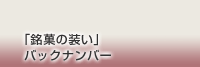![]()
風雅の味

徳島の銘菓「小男鹿」は、全国の和菓子ファンの間に、逸品として響きわたっている。「小男鹿」とはまた、よくぞこのお菓子にこの名をつけたものだと思う。
さを鹿の来立ち鳴く野の秋萩は
露霜負ひて散りにしものを
万葉集の時代から、「さを鹿」は恋路をさまよう若い男性の代名詞として歌われ、萩の花との組み合わせで、秋の優美なイメージをかきたてる言葉でもあった。銘菓「小男鹿」の上面につけられた渋い若草色の縞、断面に点々と小豆がつくりだす鹿の子斑は、巧みな「さを鹿」の表現といえよう。
しかし、なによりもこのお菓子を日本古来の心に通わせているものは、阿波特産の和三盆糖を用いてつくり出したおだやかな甘さ、ゆっくりとおなかに落ちてくるような食感である。
徳島の老舗菓子店・冨士屋が「小男鹿」を創製したのは、明治10年頃であった。冨士屋の初代喜多傳之助は、もともと江戸で10代を数えた武士だったが、明治維新後に阿波藩主蜂須賀侯にしたがって徳島に移り、「江戸餅」という菓子屋を創業した。好調だったが、所詮は武家の商法。やがて行き詰まり、そのあと屋号を冨士屋と変えて復興したのが2代目の喜多冨士太で、「小男鹿」を工夫したのはこの人である。江戸の風流が、上方の和歌の文化と出合って生まれたお菓子といっていいだろう。現在、冨士屋の当主は喜多義祐さん(昭和20年生まれ)で、5代目を数えている。
ずしりと手応えのある「小男鹿」2棹のセット。包装紙は本物の手漉き和紙である。はなだ色の厚手の和紙の表面に、白い和紙が薄く漉き込んであるが、小男鹿、冨士屋、貫禄などの文字と紅葉の葉が、はなだ色の抜きで散らしてあるという凝ったものだ。
包装を解くと、紅白の水引きで結ばれた掛け紙の見事さに驚かされる。これも手漉き和紙で、鳴門の渦潮をイメージしたという渦巻きの中に、本物の紅葉の押し葉がすき込まれていた。その中央に、墨痕淋漓と「小男鹿」の文字。
箱は淡いベージュ系の色に濃い同系色で紅葉の模様があり、蓋を開けるとさらに紋模様の透かしの入った紙包みがあって、その中から、初めて小男鹿が現れる。
枕詞「さを鹿」は、「分け入る野」を意味するが、銘菓「小男鹿」の装いには、お菓子を求めて次々に分け入ってゆく楽しさがあった。和菓子の醍醐味の一つである。
文/大森 周
写真/太田耕治
冨士屋
徳島市南二軒屋町1―1―18
088(623)1118