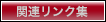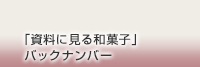ホーム > 資料に見る和菓子 第二回 No.197
 |
「引札」は江戸〜大正時代、新商品の宣伝や開店の披露などに用意された刷り物で、現在の広告ビラ、ちらしに相当します。
上の図は江戸時代の引札です。浅草雷門内にあった人気店、船橋屋織江が、このたび日本橋にも出店することになったと戯作者の仮名垣魯文が七五調のリズムのいい文章で綴っています。「風味ハ勿論お直段まで成丈骨を折詰」(骨を折る=苦心する、と、菓子の折詰を掛けている)に、「七重のひだを八重成の汁粉の御披露混交て」ご挨拶を申し上げるとあり、これは「七重の膝を八重に折る」(非常に丁寧に頼み込むこと)ということわざと、八重成(緑豆)汁粉を掛けたものです。
このように洒落や掛詞を用い、菓子名を織り込むなど、「読ませる」工夫がなされた引札の口上書(挨拶文)が多く作られました。山東京伝、式亭三馬ら文筆のプロが小遣い稼ぎに引き受けることもあり、彼らはコピーライターの先駆けといえるでしょう。
図の左側、品書きの木札を模した枠には菓子名が列記されています。「極製煉羊羹類」「上製玉あられ」など特別感を強調しており、江戸随一の商業地に支店を出すという意気込みが感じられます

さて、次は明治時代のかき氷屋のもの。氷金時、リモ氷(レモン氷)、氷ぜんざいなどのメニューの数々が目を引きます。器が入った小粋な岡持ちが描かれていて、思わず出前を頼みたくなりますね。日付は入っていませんが、「例年之通 来ル十五日より」店を開くとあり、この引札を受け取った人は「また氷の季節がきた」と心躍らせたことでしょう。

上の図でご紹介する引札は、また雰囲気がガラッと変わります。明治時代以降に作られるようになった「絵びら」とも呼ばれる色鮮やかなタイプのもので、主に年始の挨拶回りの際、お得意様に渡したといわれます。定型の図案に、あとから住所や店名などを入れるかたちをとっており、現在の社名(店名)入りカレンダーと似たような位置づけになるでしょうか。美しい絵だけでなく、長く飾ってもらえるように暦や時刻表を入れたものも残っています。

定番の図案として、美人や恵比寿・大黒などのほか、こうした店頭風景がありました。きれいな女性に目が行きがちですが、「和洋御菓子 仏事婚礼膳部菓子」を扱う菓子店の様子を示す貴重な風俗史料といえます。江戸時代に発展した刷り物の高度な技術を駆使し、近代の鮮やかな染料を使った引札は、100年以上昔のものながら、宣伝物として今見てもインパクトがあるのではないでしょうか。
より有効な宣伝をしようと先人たちが工夫を重ね、読ませるものから視覚に訴えるものへと変化していった引札。膨大な数が現存しており、画像公開をしている博物館や史料館もあります。眺めるだけでも楽しいので、ご興味のある方はぜひ検索してみてください。
(研究主任 所 加奈代)
虎屋文庫のご紹介
昭和48年(1973)に創設された株式会社虎屋の資料室。虎屋歴代の古文書や古器物を収蔵するほか、和菓子に関する資料収集、調査研究を行い、展示の開催や機関誌『和菓子』の発行を通して、和菓子情報を発信しています(現在、展示会は休止中)。資料の閲覧機能はありませんが、お客様からのご質問にはできるだけお応えしています。
HPで歴史上の人物と和菓子のコラムを連載中。
お問い合わせ
TEL:03-3408-2402 FAX:03-3408-4561
Mail:bunko@toraya-group.co.jp
URL:https://www.toraya-group.co.jp/